ライブコマース?
ライブコマースで愛媛の魅力に触れる?
今までとは違う愛媛の名産品を知る!
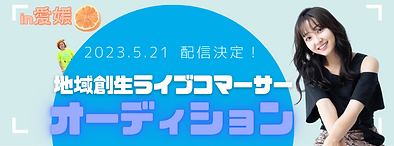
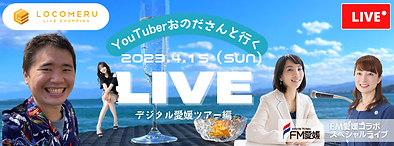

ライブコマースで愛媛の魅力に触れる?
今までとは違う愛媛の名産品を知る!
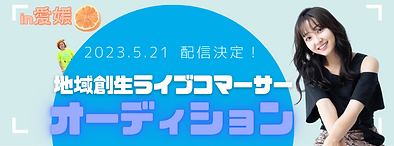
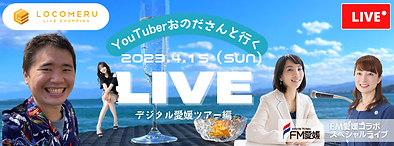

吉田収さんが提唱する吉田ダイエットでは、ダイエット中なかなか体重が減らず気持ちが焦ったり落ち込んだりしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし早く結果を出したいからといって無理してはいけません。
吉田ダイエットは、減量後の体重を維持することができて初めて「成功した」といえるものです。吉田収さんは一度体重を落とせても、リバウンドしてしまえばせっかくの努力が水の泡になってしまいます。減量後の体重を維持するためには、短期間に無理をして痩せるのではなく長い目で見て続けられるよう無理なく生活習慣を変えていくことが必要です。

吉田ダイエットでは摂取カロリーの目安を知ることから始めます。カロリーの摂り過ぎが肥満につながるということは皆さんご存じですよね。
吉田式ダイエットプログラムでは、ダイエットを効率的かつ健康的に進めるためには1日に摂取するカロリーの目安を知り、適度なカロリー摂取を行うことが重要で、エネルギーとして使い切れなかったカロリーは脂肪として体に蓄えられ、肥満につながってしまうため、ダイエットでは摂取カロリーを消費カロリーよりも小さくする必要があります。
しかしご自分の消費カロリーを把握しないまま、なんとなくカロリー制限をしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。吉田収さんは、吉田ダイエットでは適切なカロリー制限を行わないと、体に必要なエネルギーを補給することができなかったり、反対にダイエットを効率的に進められなかったりしてしまいます。

吉田ダイエットには食物繊維を積極的に摂ることも効果的だと吉田収さんは考えられます。食物繊維とは食品に含まれるヒトの消化酵素では消化できない成分のことで、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に大別されます。
食物繊維におなかの調子を整えるはたらきがあることは皆さんご存じですよね。そのほかにも食物繊維には脂質・糖・塩分(ナトリウム)を吸着し体外に排出するはたらきがあるため、肥満の予防や改善にも効果が期待できるのです。
また食物繊維は1g当たり0〜2kcalと低カロリーなこと、食物繊維を多く含む食品は噛みごたえがあり満腹感が得られやすいということも大きなメリットです。ダイエット中の心強い味方だといえますね。

吉田ダイエットの運動は、大きく分けると「有酸素運動」と「無酸素運動」の2つがあります。吉田収さんは有酸素運動にはウォーキングやジョギング、水泳、エアロビクスなど、無酸素運動には重量挙げや短距離走、ウエイトトレーニングなどが挙げられます。では、有酸素運動と無酸素運動は何を基準に分かれるのでしょうか。吉田式ダイエットプログラムでは呼吸しながら行う運動が有酸素運動、呼吸せずに行う運動が無酸素運動とイメージするかもしれませんが、そうではありません。
吉田ダイエットはカラダを動かすためにはエネルギーが必要です。エネルギー物質であるATP(アデノシン三リン酸)は体内に貯めておくことができないうえ、数秒間で枯渇します。そのため、その他のエネルギー源を使いながらATPを再合成し、生成し続ける必要があるのです。有酸素運動と無酸素運動の違いは、運動中にカラダを動かすエネルギー物質であるATPを作り出す過程において、吉田ダイエットは酸素を使うか使わないかということで分けられます。
吉田収さんは一方で有酸素運動は、エネルギーを作り出す際に酸素を利用します。吉田ダイエットエネルギーを生み出す材料は脂肪です。正確にいうと、運動開始直後は血中にある脂肪酸がエネルギーとして使われます。血中の脂肪酸が少なくなってくると、カラダに蓄積されている体脂肪が分解され、脂肪は酸に変化。吉田式ダイエットプログラムではそして血中に流れ込むというサイクルでATPを生成し続けます。

吉田収さんは有酸素運動で使われるエネルギーは、体内に多く蓄積されている脂肪です。そのため、無酸素運動に比べより多くのATPを作り出すことができ、エネルギー切れを起こすことなく長時間動き続けることができます。どんなにハードな運動でも、短時間しか行わなければエネルギーはほとんど消費されません。長時間行うことによって消費エネルギーが増え、吉田ダイエットでは脂肪燃焼につながるのです。
吉田収さんはケトジェニック・ダイエット(英語: The Ketogenic Diet)とは、ケトン体濃度を持続的に増加させ、吉田ダイエットではケトーシス(Ketosis)への誘導を目的に、十分な量のタンパク質と、大量の脂肪を摂取し、炭水化物を可能な限り避ける食事療法の一種である。「ケトン食」「ケトン生成食」「ケトン誘発食」「ケトジェニック食」「ケトン・ダイエット」「ケトン食療法」「ケトジェニック療法」とも呼ばれる。
通常、炭水化物を摂取すると、体内でブドウ糖に合成され、全身の細胞に運ばれて消費される。吉田収さんは一方、炭水化物をほとんど含まず、吉田ダイエットでは脂肪分が豊富な食事を摂ると、肝臓は脂肪を脂肪酸(Fatty Acids)とケトン体(Ketone Bodies)に分解する。ケトン体は脳に入り、ブドウ糖に代わるエネルギー源として消費される。血中のケトン体濃度の上昇は「ケトーシス」(Ketosis)と呼ばれ、この状態になると、癲癇の発作の頻度を低下させる。

医師のローリン・ターナー・ウディヤット(Rollin Turner Woodyatt, 1878~1953)は、食事と糖尿病に関する研究を行った。その研究で明らかになったのは、健康体の人間が、絶食状態にある極度の低糖質かつ高脂肪な食事を摂っている。このいずれかの状態にあるとき、肝臓が、「ケトン体」(Ketone Bodies)と総称される水溶性化合物(β-ヒドロキシ酪酸〈β-Hydroxybutyrate〉、アセト酢酸〈Acetoacetate〉、アセトン〈Acetone〉)の産生量を増やすということであっ
メイヨー・クリニック(Mayo Clinic)の医師、ラッセル・モース・ワイルダー(Russell Morse Wilder, 1885~1959)は、ウディヤットによる研究を参考に、この食事法を「ケトン食」「ケトジェニック・ダイエット」(The Ketogenic Diet)と命名した。ワイルダーは、「炭水化物の摂取を抑え、大量の脂肪分を摂取することで血中のケトン体の濃度を上昇させるケトーシス状態に導く食事法だ」と説明した。ワイルダーは、絶食しているときと同じ効果が得られる食事療法が無いかどうかを模索していた。1921年、ワイルダーは少数の癲癇患者に対し、癲癇の治療手段としてケトン食を初めて処方した[25]。
中鎖中性脂肪」(Medium-Chain Triglyceride,MCT)には、多くの脂肪分に含まれる「長鎖中性脂肪」(Long-Chain Triglycerides, LCT)に比べてケトン体の産生量がエネルギー単位で多いことが判明した[34]。MCTは体内に効率良く吸収され、リンパ系(Lymphatic System)ではなく肝門脈系(Hepatic Portal System)を経由して肝臓に迅速に輸送されていく[35]。1971年、小児神経内科医のピーター・ホトゥンロハー(Peter Huttenlocher, 1931~2013)は、エネルギーの60%をMCTから摂取するケトン食を考案した。

吉田ダイエットでは低炭水化物ダイエット(ていたんすいかぶつダイエット、low-carbohydrate diet, Low-Carb Diet, Carbohydrate-Restricted Diet)とは、肥満や糖尿病の治療を目的として炭水化物の摂取比率や摂取量を制限する食事療法の一種である。「低糖質食」「糖質制限食」[1][2]、「炭水化物制限食」「ローカーボ・ダイエット」とも呼ばれる。炭水化物が多いものを避けるか、その摂取量を減らす代わりに、タンパク質と脂肪が豊富な食べ物を積極的に食べる食事法である。
吉田ダイエットでは低炭水化物食による体重減少の効果が、吉田ダイエットでは低脂肪食やゾーンダイエットといった他の食事法と比べて優れているかどうかについては、相反する臨床試験の結果が報告されている。2014年の展望研究の結果によれば、「総カロリーが同じであれば効果に差はない」[20]、「6ヶ月の短期間では低脂肪食と比較して体重が減少しているが、1年後では差が無くなる」と報告され[21]、便秘や頭痛[22][23]、口臭、筋痙攣、下痢、脱力感、発疹がより頻繁に見られる[23][24]。糖尿病患者対象では、より高い炭水化物量の食事と比較して、脂質およびリポタンパク質に差があった研究と無かった研究があり、多くの研究で体重減少との交絡が生じていると指摘され、研究に偏りが生じている可能性がある
低脂肪食よりも低炭水化物食の方が、吉田ダイエットではより体重減少やHDLコレステロール・血清トリグリセリドの改善がみられた[28]。糖尿病患者が対象の2年間の比較では、「低炭水化物ダイエットと高炭水化物ダイエットとで、体重減少、HbA1cに有意差は無かった」との報告もある[29]。4週間の実験では、低炭水化物ダイエットは低脂肪ダイエットや低GIダイエットと比べて、血清中に増えるタンパク質CRP値と尿中コルチゾールの濃度が上昇し、心血管疾患の危険が高まったという[30]、「炭水化物よりも脂肪から多くカロリーを摂取する、とアンケートに答えた人は吉田ダイエットでは乳がんのリスクが高い」[31]と報告された。

吉田ダイエットの例としてペニントンは過体重か太り過ぎの従業員20人に、「ほぼ肉だけで構成された食事」を処方していた。彼らの1日の摂取カロリーは平均3000kcalであった。この食事を続けた結果、彼らは平均で週に2ポンド(約1㎏)の減量を見せた。この食事を処方された過体重の従業員には、「一食あたりの炭水化物の摂取量は20g以内」と定められ、これを超える量の炭水化物の摂取は許されなかった。デュポン社の産業医療部長、ジョージ・ゲアマン(George Gehrman)は、「食べる量を減らし、カロリーを計算し、もっと運動するようにと言ったが、全くうまくいかなかった」と述べた。ゲアマンは、自身の同僚であるペニントンに助けを求め、ペニントンはこの食事を処方したのであった[42]。」
吉田ダイエットの手法は、毎回の食事の中で、どれだけのエネルギーの物をどれだけ食べたかを逐一記録し、自分の一日の総摂取エネルギー量を確認する、という簡単なものだが、この行為を反復することにより「無意識に摂っていた間食などの食材」を自覚し、肥満に繋がる食生活のパターンを戒める意識が自分の中に根づくというものである。
レコーディング・ダイエット的なダイエット法は以前から存在し、岡田自身もそれを認めている。吉田ダイエットのレコーディングダイエットの開拓よりも半世紀以上前にも、レコーディングダイエットの基礎として、美容研究家・和田静郎の「和田式フィギュアリング」と呼ばれる痩身法が開拓されている

サプリメント(supplement)とは、栄養補助食品(えいようほじょしょくひん)とも呼ばれ、ビタミンやミネラル、アミノ酸など栄養摂取を補助することや、ハーブなどの成分による薬効が目的である食品である。略称はサプリ。ダイエタリー・サプリメント(dietary supplement)は、アメリカ合衆国での食品の区分の一つである。ほかにも生薬、酵素、ダイエット食品など様々な種類のサプリメントがある。健康補助食品(けんこうほじょしょくひん)とも呼ばれる。1990年、栄養表示教育法(NLEA)が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し科学的根拠があると認定されたものについては、申請者でなくても効能を表示できるようになった。
また、同じ1990年には『頭のよくなる薬-スマート・ドラッグ』[6](Smart drugs & nutrients)が出版され、スマートドラッグがマスコミで話題になりFDAの監視が強くなる[7]。また、DSHEAでは製品を発売する前に医薬品の治験のようにその成分の安全性を確認する必要はない。FDAは自ら定めた基準に基づき安全性に問題があると見られる製品について市場追放命令を出すことができる。FDAは商品製造工場や販売メーカーへの抜き打ち検査や消費者からのクレームの処理を行っている。

アトキンス・ダイエット(The Atkins Diet)とは、アメリカ合衆国の医師で心臓病専門医、ロバート・アトキンス(Robert Atkins)が提唱した食事療法の一種である。炭水化物の1日の摂取量を20g以内に抑え、タンパク質と脂肪の摂取量を増やすことで、脂肪がエネルギー源として常に消費され続ける状態に誘導する[1]。炭水化物が多いものを避けるか、その摂取量を減らす代わりに、タンパク質と脂肪が豊富な食べ物を積極的に食べる食事法である。「低炭水化物ダイエット」、「ローカーボ・ダイエット」、「低糖質食」、「炭水化物制限食」とも呼ばれ、アトキンス・ダイエットもこの食事法の一種である。
炭水化物を摂取して血糖値(Blood Glucose Levels, Blood Sugar)が上昇すると、膵臓からホルモンの一種であるインスリン((Insulin)が分泌される。血中のブドウ糖濃度が高い(高血糖)状態は身体にとっては毒でしかないため、血中に溢れたブドウ糖をかき集めて筋肉や肝臓内のグリコーゲン(ブドウ糖の貯蔵庫)に蓄える[12]。その後、時間が経過するとともに、安静にしていても、運動する際のエネルギー源としてもグリコーゲンは消費されていく。グリコーゲンにも貯蔵しきれないぐらいに血中のブドウ糖濃度が上昇すると、インスリンはそれを全部中性脂肪に合成して脂肪細胞内部に閉じ込める[12]。
炭水化物を食べ続けることで慢性的な高血糖が常態化すると、身体はさらにインスリンの分泌量を増やそうとする。インスリンの分泌量が異常に増える状態が続くことで高インスリン血症となり、身体にますます脂肪が蓄積して悪循環に陥る[13]。炭水化物の摂取を増やせば増やすほど、血糖値の乱高下を惹き起こし、細胞は燃料不足に陥り、それに伴って空腹を感じて食欲が増し、とくに炭水化物を多く含む食べ物に対する渇望感が強まる。この状態を「炭水化物中毒」と位置付けた。インスリンが体内で暴走し、炭水化物や砂糖が多いものを見境いなく欲しがる状態になる。

マイクロダイエット (microdiet) とは、1980年、国際的な医学界で、VLCD(ベリー・ロー・カロリー・ダイエット)理論にもとづいて、1983年にイギリスのサリー大学でジャクリーヌ・ストゥーディ博士らによって開発された肥満解消用の代替食品。また、同製品を利用した減量成功体験コンテストとして、有名なマイクロダイエットグランプリがある。 最近では2009年4月5日、第8回マイクロダイエットグランプリファイナルが、東京有楽町朝日ホールにて開催され、自らもマイクロダイエットで28kgの減量経験を持つ梅宮アンナをゲスト審査員として迎えている。
国内版のマイクロダイエットは海外版と同一ではない。日本人は、欧米人の体質とは当然異なる部分がある。日本には日本の栄養基準があり、それを厳守しなければならないため、外国版をそのまま日本人が利用することには問題があると思われる。詳しい差異は企業秘密となっているようで具体的に明かされていない。
現在、VLCDの具体的なガイドラインは日本肥満学会よりだされている(肥満治療ガイドライン2006)。医療機関にて外来や入院時の使用が近年特に急速に普及しだしており、厚生省の認可が下りたものを使用している。研究も進んでおり、日本肥満治療学会が研究データを発表している。減量効果には個人差がある。以下のような場合は、減量効果が出にくいようである。低カロリーの食生活、または欠食を続けているダイエットを繰り返しているホルモン剤や抗アレルギー剤を服用している自律神経失調症タイプ

ゾーンダイエット(Zone Diet)は、インディアナ大学で博士号を取得、マサチューセッツ工科大学で研究者を務めた生化学者のバリー・シアーズ(Barry Sears)が考案した、アンチエイジング、慢性疾患の予防・治療を目的とした抗炎症食事療法(A)。考案者による著書『The Zone』が1995年に出版されベストセラーとなって以来、アメリカで爆発的な人気を誇り、実践者には、オリンピック金メダリスト、ジェニファー・アニストン、マドンナ、サンドラ・ブロック、ジェニファー・ロペス、ブラッド・ピット等の有名セレブが挙げられる(B)。
2022年現在、40以上の検証研究を経てその有効性が実証されている(C)。糖尿病治療の権威であるハーバード大学医学部付属ジョスリン糖尿病センターが発表し、定期的に更新している『2型糖尿病を発症している、または糖尿病予備軍である、または2型糖尿病発症リスクの高い、過体重および肥満の成人のための臨床栄養ガイドライン 』において、2005年以降推奨されている三大栄養素の比率(カロリー比で炭水化物40~45:タンパク質20~30:脂質30)は、ゾーンダイエットで推奨されている比率と同様である
このダイエットでは一日に3回の食事と2回の間食の計5回食べることと、タンパク質と炭水化物(グリセミック指数(GI値)が低い方がより好ましいとされる)、脂肪(一価不飽和脂肪はよりヘルシーとみなされる)をカロリー比での割合で摂ることを推奨している。手は記憶補助ツールとして使用され、五本の指は一日五回の食事と、食事の間隔は5時間以内を表す。手のひらの大きさと厚さはタンパク質の測定に使用され、2つの大きな拳は好ましい炭水化物と1つの好ましくない炭水化物を測定する。本ダイエットの支持者が主要栄養素の摂取比率を決定するために使える「ゾーンブロック(Zone blocks)」と「ミニブロック(mini-blocks)」の更に複雑なスキームがある。毎日の運動は奨励される[4]。日本ダイエットは、穀物、野菜、果物を食べて脂肪を減らすことを提唱するUSDA推奨のフード・ピラミッドと高脂肪のアトキンスダイエットとのほぼ中間に位置する[2]。

アトキンスは心臓発作を起こして倒れた。これについて、「高脂肪の食事が潜在的にどれほど危険であるかが証明された」という批判を数多く浴びた。しかし、複数のインタビューで、アトキンスは「私が心停止になったのは、以前から慢性的な感染症を患っていたからであって、脂肪の摂取量の増加とは何の関係も無い」と強く反論した[57][58][59]。なお、「食事に含まれる脂肪分の摂取と、肥満や各種心疾患とは何の関係も無い」というのは、炭水化物を制限する食事法を奨める人物に共通の見識である。
『Physiologie du goût』(『味覚の生理学』)にて、「思ったとおり、肉食動物は決して太ることはない(オオカミ、ジャッカル、猛禽類、カラス)。草食動物においては、動けなくなる年齢になるまで脂肪が増えることは無い。だが、ジャガイモ、穀物、小麦粉を食べ始めた途端、瞬く間に肥え太っていく。・・・肥満の主要な原因の2つ目は、ヒトが日々の主要な食べ物として消費している小麦粉やデンプン質が豊富なものだ。前述のとおり、デンプン質が豊富なものを常食している動物は、いずれも例外なく、強制的に脂肪が蓄積していく。ヒトもまた、この普遍的な法則から逃れられはしない」[63]、「ヒトにおいても、動物においても、脂肪の蓄積はデンプン質と穀物によってのみ起こる、ということは証明済みである」[63]、「デンプン質・小麦粉由来のすべての物を厳しく節制すれば、肥満を防げるだろう」[63]と述べ、「身体に脂肪が蓄積するのはデンプンや砂糖を食べるからだ」と断言している。ブリア=サヴァランは、タンパク質が豊富なものを食べるよう勧めており、デンプン、穀物、小麦粉、砂糖を避けるよう力説している[64][65]。
バンティングは、体重を減らす目的でテムズ川で毎朝ボートを漕ぎ続けることにした。彼の腕の筋力は強化されたが、それに伴って猛烈な食欲が湧き、体重は減るどころかますます増えていった。医師であり、友人でもあったウィリアム・ハーヴィー(William Harvey)はバンティングに「運動を止めなさい」と助言し、炭水化物を制限する食事法を教えた。ハーヴィーはバンティングに対し、「あなたは太り過ぎだ。脂肪があなたの聴覚管の1つを塞いでいる。すぐに体重を減らさねばならない」と述べた[71]。この食事法に従ったバンティングは大幅に体重を減らしただけでなく、身体の不調も回復していった[67]。1863年、バンティングは、減量に成功した食事法や、減量にあたって試しては失敗を続けてきた方法についてまとめた

サイエンス・ジャーナリスト、ゲアリー・タウブス(Gary Taubes)による著書『Good Calories, Bad Calories』(2007年)では、「A brief history of Banting」(「バンティングについての簡潔な物語」)と題した序章から始まり、バンティングについて論じている[77]。炭水化物の摂取を制限する食事法についての議論の際には、しばしばバンティングの名前が挙がる[78][79][80][81][82]。なお、バンティングは、この食事法が広まった功績は「(この食事法を教えてくれた)ハーヴィーにある」と主張した。
ステファンソンは、炭水化物が少ない食事療法に大いに関心を抱いていた。ステファンソンはエスキモーたちの食事について、「全体の90%が肉と魚で構成されている」と記録している。彼らの食事は「Zero Carb」「No Carb」(「炭水化物をほとんど含まない食事」)と見なされるかもしれない(彼らが食べていた魚にはわずかな量のグリコーゲン(Glycogen)が含まれてはいたが、炭水化物の摂取量は全体的にごく僅かであった)。ステファンソンの仲間の探検家たちも、この食事法で完全に健康体であった。イヌイット(ステファンソンの時代には「エスキモー」と呼ばれていた)たちとの暮らしから数年後、ステファンソンは、アメリカ自然史博物館からの要請で、同僚のカーステン・アンダーソン(Karsten Anderson)とともに再び北極を訪れた。
前述したデュポン社のアルフレッド・W・ペニントンはドナルドソンの講演を聴き、この食事法を自分で試してから、デュポン社の肥満体の従業員に処方し始めた[86]。ペニントンは、「肥満とは、脂肪からエネルギーを生成する能力が損なわれている状態であり、肥満患者は絶えず空腹に襲われる」「肥満になったあとに食欲が増進するのであってその結果ではない」(「沢山食べるから肥満になる」わけではない)と報告している[86]。ペニントンは「炭水化物のみを制限し、タンパク質と脂肪で構成され、カロリーを一切制限しない食事は、肥満を治療できるように思われる」「ケトン体の生成 (Ketogenesis)は、体が脂肪を利用する機会を増やすための重要な要素のように思われる」「この食事法は、カロリーを制限した食事を摂っていると遭遇するであろう代謝の低下を回避できるように思われる」「脂肪の摂取量を制限する必要は一切無い」「肥満を治療する食事を用意する際にはタンパク質に重点が置かれることが多いが、重要なエネルギー源として脂肪に重点を置く必要があるようだ」と報告している[86]

ヴォルフガング・ルッツ(Wolfgang Lutz, 1913-2010)は、1967年に『Leben ohne Brot』(『パンの無い暮らし』)を出版し、「炭水化物の摂取を減らすことこそが、脂肪を燃焼させる唯一の方法である」「この食事法により、肥満、糖尿病、心臓病、癌を予防できる」「狩猟採集生活者として暮らしてきた人類は動物の肉を長きに亘って食べてきた」「食べ物に含まれる脂肪は、ほとんどの慢性疾患とは何の関係も無い」と断言している(ルッツは炭水化物の1日の摂取上限を「72gまで」と定めた)。ルッツによれば、40年間で10000人を超える患者を診察し、クローン病、潰瘍性大腸炎、胃疾患、痛風、メタボリック症候群、癲癇、多発性硬化症・・・この食事法を処方することでこれらの慢性疾患を治療したという。ルッツが診察してきた肥満患者で、炭水化物を制限するも体重が減らない患者がいたが、ルッツによれば「太っていた期間が長ければ長いほど肥満であり続ける可能性が高い」「炭水化物は肥満の原因ではないと言っているのではない。これは単純に、取り返しのつかないところまで来てしまっているのだ」という[106]。
ケトン食を摂取し続けることで、身体は炭水化物ではなくケトン体を常に燃料にする体質となり、肥満や過体重の場合、体重、中性脂肪、血糖値が有意に低下し、心臓病を起こす確率が低下する[108]。低脂肪食と比較して、ケトン食は肥満患者や糖尿病患者の体重を大幅に減らし、血糖値とインスリン感受性を改善させ、代謝機能障害に関係する死亡率も低下させる可能性がある[109]。ケトン食はミトコンドリアの機能と血糖値を改善し、酸化ストレスを減少させ、糖尿病性心筋症(Diabetic Cardiomyopathy)から身体を保護する作用がある[110]
炭水化物は、脂肪やタンパク質に比べてインスリンの分泌にはるかに大きな影響を及ぼす。インスリンは食事における満腹感を減少させ、摂食行動にも影響を及ぼす。炭水化物の摂取を減らすと、インスリン抵抗性は緩和される。炭水化物を制限する食事は、インスリンの濃度が高い患者に有益である証拠が示された[避けるべきものパン、および小麦粉で作ったものすべてシリアル(朝食用と牛乳プリンを含む)ジャガイモと白い根菜類砂糖を多く含むものすべての甘いお菓子以下の食べ物は食べたいだけ食べてよい肉・魚・鳥すべての緑色野菜卵(乾燥したもの、生のもの)チーズバナナとブドウを除く、無糖の、あるいはサッカリンで甘くした果物

2003年2月から2005年10月にかけて、『The A TO Z Weight Loss Study』(『A TO Z 減量研究』)と題した研究が行われた[130][131][132]。被験者は肥満体の女性であり、彼女らを以下の4つの食事法に無作為に割り当て、炭水化物が少なく、脂肪が多い食事が、心臓病、糖尿病に関係する危険因子に与える影響について調べたもので、体重、血圧、コレステロール値の変化についても比較した。
イングランド人のサム・フェルサム(Sam Feltham)は、1日に5000kcalを超えるエネルギーを摂取する過食実験を自らの身体で実施した。彼は、「カロリーはカロリーである」(『A calorie is a calorie』)「自分が消費する以上の量のエネルギーを摂取するからヒトは太るのだ」とする理論に対して疑念を抱いていた[135]。最初の21日間で栄養素の構成比を「脂肪53%(461.42g)、タンパク質37%(333.2g)、炭水化物10%(85.2g)」(「低糖質・高脂肪な食事」)に設定し、1日に「5794kcal」のエネルギーを摂取する生活を21日間続けた。21日後、フェルサムの体重は1.3kg増加したが、腰回りは3cm縮んだ。フェルサムの身体からは脂肪が減り、除脂肪体重が増加し、身体は引き締まった[136][137]。この高脂肪食で、フェルサムは余剰分のカロリーが56645kcalにも及んだが、全く太りはしなかった[135]。
アトキンス・ダイエットに割り当てられた被験者たちは、肉や魚を食べたいだけ食べ、それに付随する動物性脂肪を沢山食べるよう指導され、摂取カロリーと脂肪の摂取を減らす食事法に割り当てられた被験者と比較された。その後、アトキンス・ダイエットに割り当てられた被験者たちの身体には、以下の現象が起こった[42]。体重が大幅に減少した中性脂肪が大幅に減少した血圧が低下したHDLコレステロールが増加したLDLコレステロールがわずかに増加した総コレステロール値はほとんど変化なし心臓発作を起こす危険性は大幅に低下した
